日時;2018年12月2日(日)10:30~14:30
会場;公津の杜コミュニティセンターもりんぴあこうづ
参加者;25名
暖冬であたたかな冬の例会。午前の部は、今年の8月に行われた第34回全国大会(鹿児島大会)での実践報告を、発表者の船橋市立坪井小学校 学校司書 中村貴子さんに報告していただきました。午後の部は同じく鹿児島大会の分科会「学校図書館のためのプライバシー・ガイドライン」に参加した千葉日本大学第一中学・高校 島津直美さんから分科会の概要を伺ったあとに、ガイドラインに沿って自校の学校図書館と照らし合わせてみました。
午前の部;「実践報告~学校図書館の日常的な活用で学びを深める」
<はじめに>
電子媒体が普及し、紙媒体を読む人は減っており、学校生活、塾、習い事で子供たちは多忙になっているが、学校司書は読めるようになってほしい!と願っている。学校図書館を日常的に利活用することをきっかけとして、自然に「読みたい」気持ちと本好きを育て中学校以降の利用につなげたい。そのためには学校司書一人ではなく司書教諭をはじめとした教職員、図書委員、保護者ボランティアと協力して取り組むことが必要。

<図書委員会の活躍>
全校生徒が本好きになるように広報活動をしている。特に図書の時間が取れない高学年の自分のクラスの児童が学校図書館を利用するように取り組んでいる。(本の選抜総選挙、読書しりとり、先生へのおすすめ本インタビューなど)
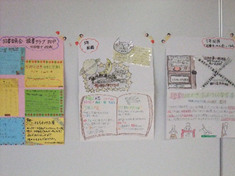
この後、添付資料を参考に授業例をパワーポイントで説明していただきました。
<授業例>
小学1年「としょかんへいこう」、小学6年「リテラチャー・サークル」、小学4年「読書発表会」をしよう、 小学2年「図書館で本を探そう」、小学4年「分類をもとに本を見つけよう」、小学2年「生きもののことを せつめいしよう」、小学3年「野菜博士になろう」など
子どもたちの生き生きとした活動が伝わる写真資料に参加者たちの熱い視線が注がれていました。(詳しくは 『がくと』Vol.34鹿児島大会 学校図書館問題研究会12月頃発行予定 に掲載されます)
成果 ・多くの児童が本を借り読書を楽しんでいる。身近な疑問を解くためにも本を使
う。
・図書委員の活動が他の学年にも広がっている。
・学習関連の本も率先して借りていき、担任に紹介しており、「調べる学習が好き」
という児童がいる。など
課題 ・利活用に個人差、学級差、学年差がある。
・高学年の読書の問題:読めない子、読まない子、背伸びをした読書・・・
・インターネットと本の使い分け、両方を上手く使いこなせるようになってほしい。
・学習での図書資料や学校図書館活用はもっと増える余地があるので更に働き
かける。:研修等で知り得た情報を先生方に伝え共有する。など
【質問】
Q.選書がとても重要というお話でしたが、選ぶ際に参考にしているものはなんですか?
A.公共図書館に現物を見に行く。教文館ナルニアに見に行く。子どもの本研究会や親
地連の冊子等を参考にしています。
Q.ラベルは2桁ですか?
A.現状は2桁です。市内では古くから小学校は2桁、中学校は3桁で統一してきました。教科書には3桁の例も入ってきているので、変更すべきか迷いますが、するなら市内一斉となるでしょう。その作業に要する時間を考えると今は無理かと思います。
写真資料や実物資料をふんだんに用意されて、たいへん丁寧に説明していただきました。
中村さんありがとうございました!
午後の部; 分科会「学校図書館のためのプライバシー・ガイドライン」をうけて 島津直美さん
<概要>
最初に沖縄国際大学教授 山口真也先生の講演がありました。内容は「今年4月 NHK番組プロフェッショナル仕事の流儀で、学校図書室の貸し出しカードに記された生徒の氏名などが読み取れる状態だったとして、学校図書館問題研究会がNHKに対し配慮を求めた。世間では“そんなに騒ぐことなの?”という程度の受け止められかたである。しかし学校司書は専門職。自覚をもって個人情報を取り扱ってほしい。この話を職場に持ち帰りプライバシー・ガイドラインの作成を学校側に提言してほしい」との趣旨でした。
分科会での質問やグループ討議の内容
・男女別の名簿は必要か?
・貸し借りのデータを残さない?
・冊数を公表することは必要か?多読賞は必要か?
・児童・生徒がカウンター業務をするのはプライバシー保護の観点からやめるべき?
・見守りが必要な生徒・児童の来館や貸し出しに対する先生の呼びかけにもプライバシー
の観点から言えば答えられない?
・督促の用紙には冊数や書名などを出さない? → 先生からなぜ冊数や書名が出せない
のかと苦情があった学校も。
島津さんの報告をうけて、各班に分かれ模造紙と付箋紙を使って問題点をマッピングしながら、それぞれの学校の現状を話し合いました。
千葉支部でのグループ討議
・学校司書自身が図書館でプライバシーを扱っているという認識を持つこと。学校の先生
方にもお話ができるとよい。
・児童・生徒のカウンター業務については人手が不足しておりやむを得ない状況がある学
校も。その際はプライバシーをきちんと守るように年度当初に必ず話をする。
・男女別の名簿は、廃止した学校も。
・督促状を出す場合は、書名を隠す、学校司書が自ら行くなどの配慮をしている人もいる
一方、借りている本を延滞している のだから教員からきちんと指導してもらう必要があ
るので書名もきちんと出すという人も。
・来館した児童・生徒に生徒指導上の問題がある場合には、司書一人で抱え込まず担任の先生はじめ他の先生に相談することで事故を未然に防ぐことにつながることがある。
・貸し出し冊数の開示などは、その用途が重要。ただ単に数を報告するのではなく、児童・生徒の成績にかかわるなど教育に必要な場合は応じることにしている人も。

現状ではガイドラインにぴったり沿うのは難しいけれども、学校司書としてプライバシーに関しては敏感でありたいというのが一致した意見でした。
